

在留資格「技能実習」の概要
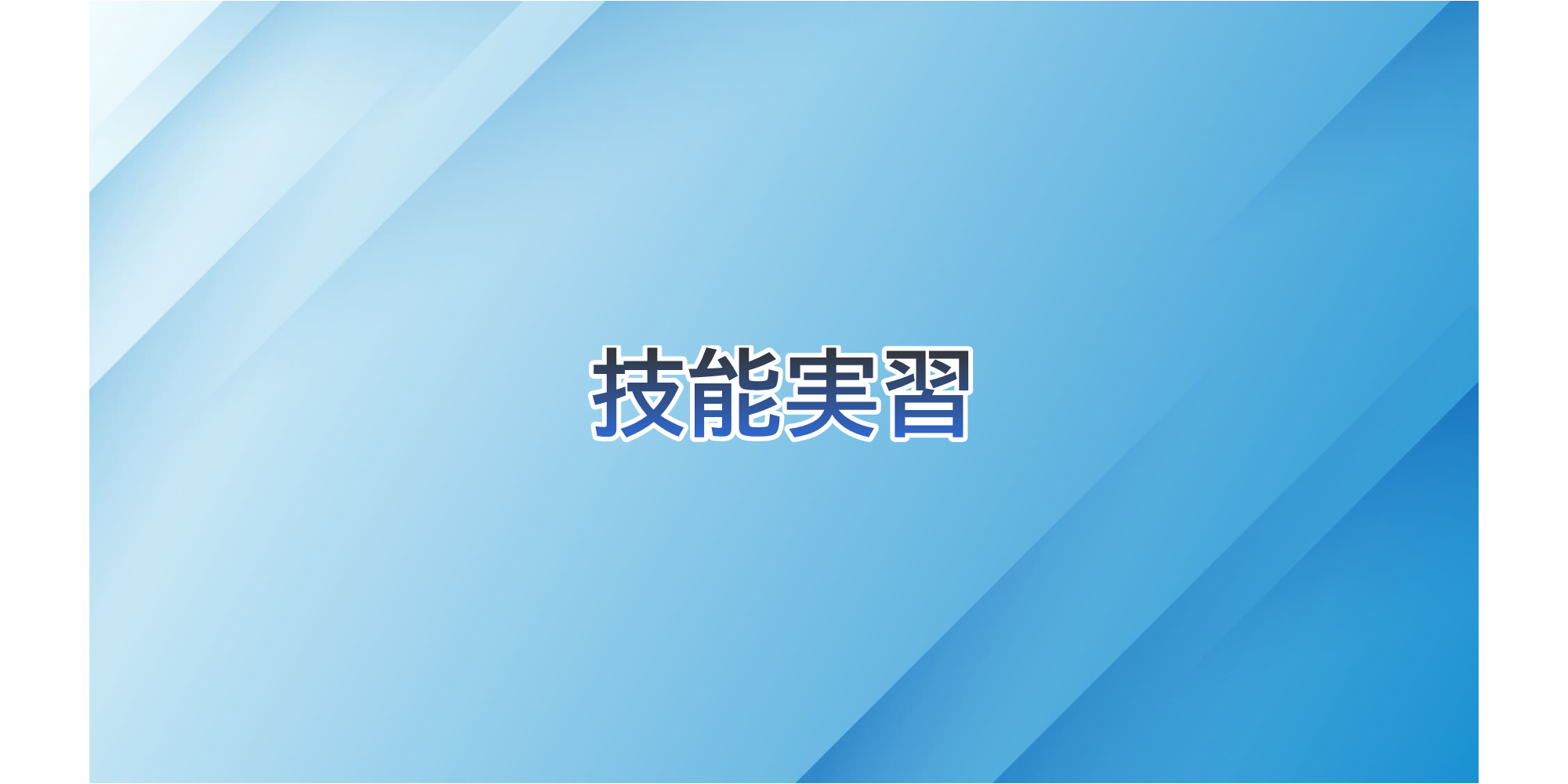
目次
はじめに
技能実習制度は、1993年に本格的に始動し、日本で在留する外国人が報酬を伴いながら技術や知識を習得することを目的とした制度です。日本企業が海外への技術移転や国際協力を進める中で、同制度は教育的側面と実務の両立を図る重要な仕組みとして運用されてきました。現在、制度は多数の実習生を輩出していますが、労働環境の問題や人権保護の側面から、2027年の廃止と新たな育成就労制度への移行が検討されています。
技能実習制度の概要
技能実習制度は、出入国管理及び難民認定法別表第一の二に基づき、在留資格「技能実習」で日本に滞在する外国人が、実践的な技能や技術を習得しながら働く仕組みです。受け入れ体制は大きく2つの形態に分かれ、企業単独型と団体監理型により、実習生の受け入れ方法や人数の上限が異なります。また、制度内では実習期間が段階的に区分され、初年度の「技能実習1号」、2~3年目の「技能実習2号」、さらには4~5年目の「技能実習3号」といった形で、各段階ごとに習熟度が評価されます。
以下の表は、企業単独型と団体監理型における実習の区分と呼称の例です。
| 実習期間 | 企業単独型 | 団体監理型 |
|---|---|---|
| 1年目 | 技能実習1号イ | 技能実習1号ロ |
| 2~3年目 | 技能実習2号イ | 技能実習2号ロ |
| 4~5年目 | 技能実習3号イ | 技能実習3号ロ |
制度は、実習生が一定期間内に技能や技術を十分に習得できるよう、研修と現場での実務体験を組み合わせたプログラムとなっており、各段階で技能検定基礎2級相当の試験合格など、一定の要件を満たすことが次のステップへの移行条件となっています。
制度の理念と仕組み
この制度の基本理念は、日本の高度な技術や知識を途上国に移転し、経済発展を支える人材の育成に寄与することにあります。同時に、実習生が安全かつ安心して技術の習得に専念できる環境を整備することが求められています。具体的には、実習内容の適正な管理や、労働者としての保護措置が講じられており、実習生がその本来の目的から逸脱することなく技能の向上に集中できる仕組みとなっています。
また、制度運用にあたっては、企業単独型と団体監理型といった受け入れ方式により、各受入れ機関が適切な管理体制のもと、実習生の生活や労働環境の確保を義務付けられている点が特徴です。
外国人研修制度との位置づけ
当初、1981年に創設された外国人研修制度は、日本企業の海外進出に伴い、現地社員を対象として技術移転を進める目的で導入されました。これを背景に、1993年には実際に報酬を伴う「技能実習制度」が整備され、研修生は一定期間の講習や実習を経て、現場での実践的な技能を身に付ける仕組みとなりました。研修期間が最初は短期間であったものの、1997年の改正により最長3年に延長され、後の法改正により労働者としての保護措置も強化されました。
沿革と歴史
技能実習制度の歴史は、1981年の外国人研修制度創設に始まります。日本企業が海外現地法人から技術習得を目的として現地社員を招聘した事例を背景に、専門人材の育成を目的とする制度として位置づけられました。1990年代初頭には、出入国管理法の改正により研修の在留資格が整備され、1993年に技能実習制度として正式に運用が開始されました。
その後、1997年の改正では実習期間が最長3年に延長され、2010年には出入国管理及び難民認定法の改正に伴い、「研修」と「技能実習」の位置づけが再編され、実習期間中の労働者保護が強化されました。さらに、2017年には実習生の適正な管理を目的として「外国人技能実習機構」が設立され、2019年からは特定技能への移行も進められるなど、社会的な議論と共に制度の改変が続いています。
数年間で実習生の移行申請者数は大幅に増加し、制度の運用状況や各種問題点の指摘を背景に、近年は改善策や監視体制の強化が各省庁・関係団体により進められてきました。
入管法改正と受入れ方式
2009年~2010年にかけての入管法改正は、技能実習制度における実習生の権利保護や労働環境の改善に大きな影響を与えました。改正により、実習期間中の最低賃金や労働時間など労働法令の適用が明確化され、不正行為への罰則や受入れ禁止措置が強化されました。また、受け入れ方式としては、企業単独型と団体監理型の二つがあり、各方式で受け入れ可能な人数や管理方法が異なります。特に団体監理型では、複数の受入れ企業と連携する形での監督体制が整備され、研修生の保護をより一層推進する仕組みが整えられています。
近年は、受け入れ仲介業者による不正事例の摘発や、コロナ禍における再就職支援策など、現場での運用に対する監視体制も強化され、制度の透明性向上に向けた取り組みが続いています。
今後の展望と育成就労制度への移行
技能実習制度は、これまで多くの外国人実習生を受け入れ、日本の技術・知識の国際伝達に貢献してきました。しかし、長期にわたる実習の中で労働環境や人権保護の問題が指摘され、制度の抜本的な見直しが求められるようになりました。政治・経済の両面から、現行制度の見直しと改善が進む中、2027年廃止を視野に入れた新たな在留資格「育成就労制度」への移行が検討されています。
新制度では、実習生の技能習得だけでなく、労働者としての権利保護やキャリア形成をより一層支援する仕組みが整備される見通しです。企業や支援団体、そして行政と連携しながら、より公正で持続可能な受け入れ環境の構築が求められています。
まとめ
本記事では、1993年に始まった技能実習制度の基本的な仕組み、理念、そしてこれまでの沿革や法改正の流れについて詳しく解説しました。制度は、日本の国際協力の一翼を担い、多くの実習生が技術や知識を習得するための重要な枠組みとして機能してきましたが、労働環境や人権保護といった課題が浮上する中、2027年廃止・育成就労制度への移行が検討されています。
行政書士や企業の担当者にとって、制度の変遷や最新の改正内容を正しく把握することは、適正な手続きの遂行と実習生の保護につながります。今後も制度の動向に注視し、最新情報を踏まえた対応が求められるでしょう。
