

在留資格「特定技能」の概要
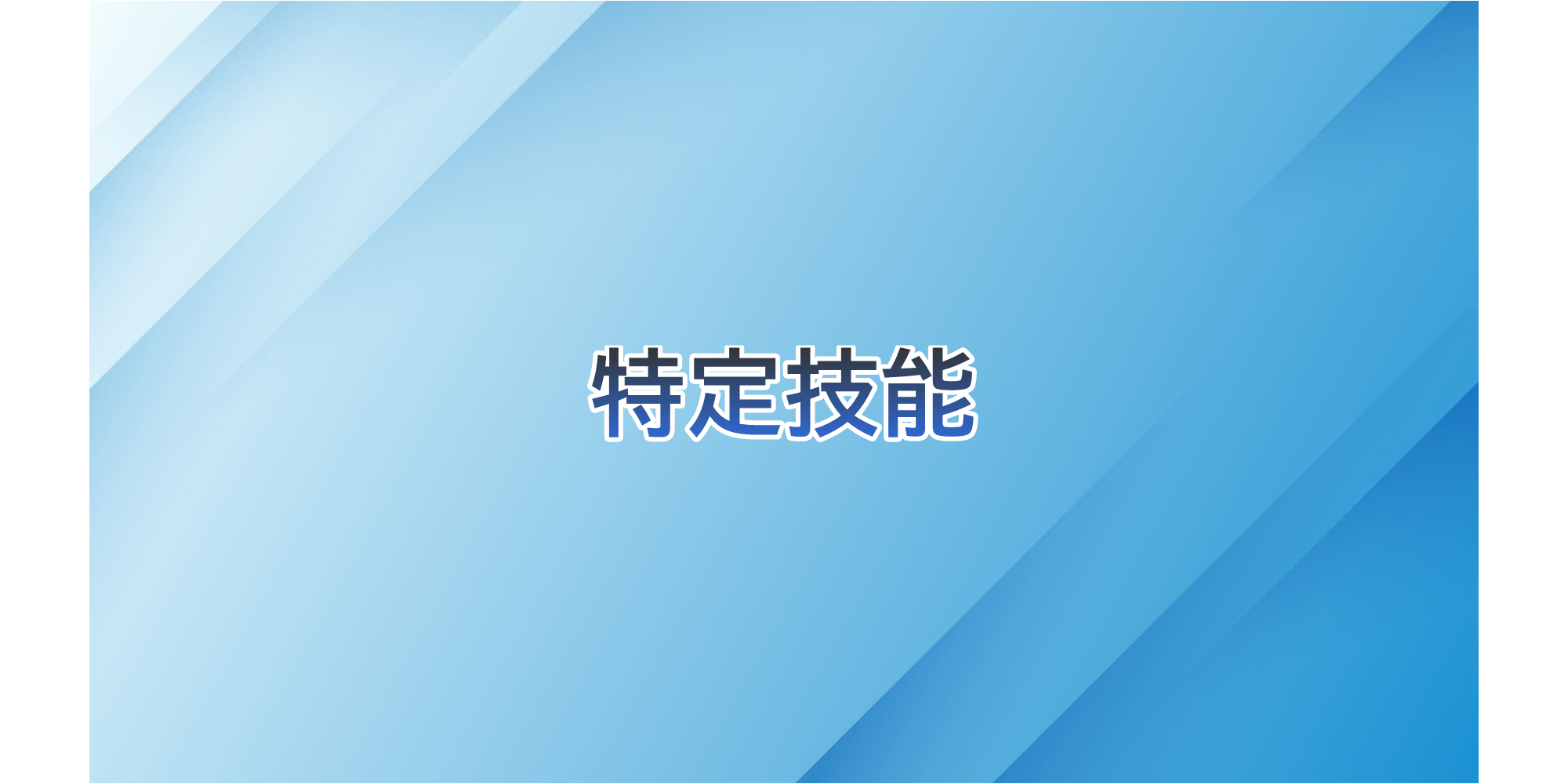
目次
はじめに
在留資格「特定技能」制度は、2018年の改正出入国管理法に基づき、2019年4月から本格的に始動しました。日本国内で深刻化する人手不足に対応すべく、一定の専門性や技能を有する外国人の受入れを促進するために設けられたこの制度は、企業活動や産業の発展に寄与することを目的としています。
本記事では、制度の概要や受入れ対象の産業分野、外国人支援体制、各種申請手続きまで。最新の改正点も踏まえながら、行政書士事務所の視点から分かりやすく解説します。
在留資格「特定技能」とは
「特定技能」制度は、深刻な人手不足が続く産業分野において、一定の専門技能や知識を持つ外国人労働者を受け入れるために創設されました。制度上は、特定技能1号と特定技能2号という2種類の在留資格に分かれており、それぞれ求められる技能水準や在留期間、家族帯同の可否について明確な違いがあります。
| 項目 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
|---|---|---|
| 在留期間 | 法務大臣が個々に指定(原則1年以内) | 最長6か月、1年、または3年(業務内容により異なる) |
| 技能評価 | 試験等により確認(技能実習2号修了者は一部試験免除) | より厳格な技能認定が求められ、免除対象もあり |
| 日本語能力 | 日常生活と業務に必要なレベルを試験で評価 | 特殊な検定は必要とせず、実務上の判断で対応 |
| 家族帯同 | 基本的に認められない | 一定の要件を満たせば認められる |
このように、特定技能1号は比較的基準が明確で幅広い産業分野での外国人活用を促す一方、特定技能2号はより高度な技能が要求される業務を対象としています。
特定産業分野について
制度の受入れ対象となる分野は、日本の生産性向上および国内人材確保のための取り組みが進んでもなお、十分な人材確保が困難とされる産業に限定されています。具体的には、介護、ビルクリーニング、工業製品製造、建設、造船、自動車整備、航空、宿泊、自動車運送、鉄道、農業、漁業、飲食料品製造、外食、林業、木材産業の16分野が設定されており、特定技能2号の対象分野はその中から11分野とされています。
なお、2024年3月29日の閣議決定およびその後の関係省令改正により、自動車運送業、鉄道、林業、木材産業が新たに加えられるとともに、工業製品製造業の一部業務区分の名称変更等が行われ、制度の運用が更に進化しています。
受入れ機関と登録支援機関
特定技能制度において、実際に外国人労働者を受け入れる事業者や個人事業主は「受入れ機関(特定技能所属機関)」と呼ばれます。受入れ機関は、外国人との雇用契約(いわゆる「特定技能雇用契約」)を締結し、日本人と同等以上の報酬を支払うなどの基準を満たす必要があります。また、外国人労働者がスムーズに日本で生活し業務を遂行できるよう、支援体制の整備が義務付けられています。
さらに、受入れ機関が全ての支援業務を行うことが困難な場合には、政府の認定を受けた「登録支援機関」に業務の一部または全部を委託することが可能です。登録支援機関は、支援責任者および担当者の配置や法令遵守の基準をクリアし、定期的な届出義務を果たすことで、その適正さが維持されます。
外国人支援の具体的内容
受入れ機関および登録支援機関が提供する支援は、多岐にわたります。まず、入国前には生活ガイダンスを多言語で実施し、空港での出迎えや帰国時の見送り、住宅確保のための保証人の役割も果たします。日本での生活開始後は、口座開設や携帯電話契約などのオリエンテーション、日常生活に必要な日本語学習支援、さらには各種行政手続きに関する情報提供が行われ、定期的な面談による状況確認や相談窓口の設置など、全人的なサポート体制が整備されています。
申請手続きと政府間の取決め
在留資格「特定技能」を取得するためには、在留資格認定証明書の交付申請、在留資格変更許可申請、在留期間更新申請など、複数の手続きが必要となります。また、外国人労働者の受入れにあたっては、受入れ機関や登録支援機関の登録申請が求められており、JITCOによる点検・取次サービスが利用できるなど、申請手続の円滑化も図られています。
一方で、日本政府は特定技能外国人の受入れに関連し、主要な送出国との間で二国間取決めを締結しています。これにより、悪質な仲介業者の排除や情報共有の枠組みが強化され、各国政府が認定する送出機関を通じて外国人労働者の手続きが厳格に管理されています。
分野別所管省庁および試験実施機関
特定技能の各産業分野では、担当する所管省庁が運用方針や試験実施の基準を定めています。たとえば、介護分野では厚生労働省が試験を策定し、ビルクリーニング分野では公益社団法人が窓口となっています。工業製品製造業や建設分野、さらには航空や農業分野など、各業界ごとに専用の試験実施機関が存在し、候補者の技能や日本語能力の評価が厳格に行われています。
| 分野 | 所管省庁 | 試験実施機関/情報掲載先 |
|---|---|---|
| 介護 | 厚生労働省 | 介護技能評価試験等実施事業者 |
| ビルクリーニング | 厚生労働省 | 公益社団法人 全国ビルメンテナンス協会など |
| 工業製品製造業 | 経済産業省 | 経済産業省が選定した試験実施機関 |
| 建設 | 国土交通省 | 一般社団法人 建設技能人材機構 |
まとめ
在留資格「特定技能」制度は、日本の人手不足解消に向け、一定の技能を持つ外国人の受入れを支援するための重要な仕組みです。特定技能1号と2号の二つの枠組みにより、求められる技能レベルや滞在期間、家族帯同の可否などが明確に区分されており、適切な支援体制の下で外国人労働者が日本で活躍できる環境が整えられています。また、受入れ機関や登録支援機関の厳格な基準、各種試験制度、そして政府間の協定により、制度全体の透明性と安全性も高められています。
最新の制度改正や運用状況を踏まえると、今後もより良い外国人材受入れ環境の整備が期待されるとともに、企業や関係機関には引き続き、法令遵守と適切な支援の実施が求められるでしょう。
